親族内承継の実態と実践 成否を分ける3つのポイント
公開日:2025年5月22日
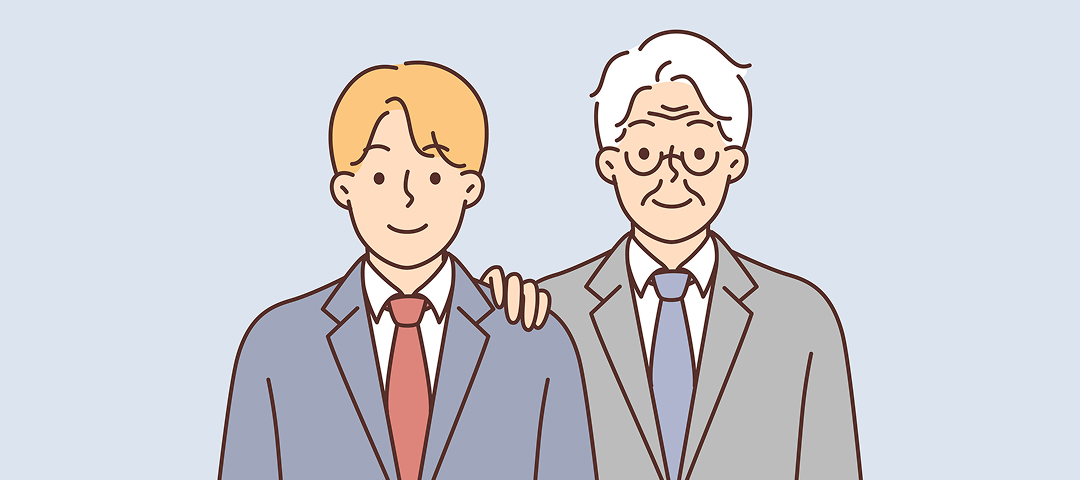
事業承継を検討している方の中には、親族内承継を考えているケースも多いのではないでしょうか。本記事では、親族内承継の現状、引き継ぎの流れや成功のポイントをご紹介します。
親族内承継とは?
親族内承継は、日本では古くからおこなわれている伝統的な承継の形態です。子どもや親族に事業を引き継ぐため、企業の経営理念や価値観を引き継ぎやすい一方、後継者の育成や相続・税務対策が課題となるケースも少なくありません。
なお、事業承継には親族内承継以外にも「従業員承継」「M&A(第三者承継)」の選択肢があります。事業承継全般については、以下の記事をご覧ください。
3割以上の企業が親族内承継を選択
親族内承継は、従来日本で最も多い事業承継の形態でした。帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2024年)」によると、2023年までは他の形態と比較し、親族内承継が最も高い値を示しています。2024年の速報値では32.2%となり、内部昇格(36.4%)を下回ったものの、3割以上の企業が依然として親族内承継を選択しています。
![全国 代表者・就任経緯別推移(2020年以降) 親族内承継[2020年]39.3%、[2021年]38.7%、[2022年]37.6%、[2023年(実績值)]36.0%、[2024年(速報値)]32.2% 内部昇格[2020年]31.9%、[2021年]31.4%、[2022年]33.3%、[2023年(実績值)]34.4%、[2024年(速報値)]36.4% M&Aほか[2020年]17.2%、[2021年]18.6%、[2022年]18.6%、[2023年(実績值)]19.4%、[2024年(速報値)]20.5% 外部招聘[2020年]7.6%、[2021年]7.3%、[2022年]7.1%、[2023年(実績值)]6.9%、[2024年(速報値)]7.5% 創業者[2020年]4.0%、[2021年]4.0%、[2022年]3.4%、[2023年(実績值)]3.3%、[2024年(速報値)]3.4% [注1]2022年までの数値は、過去調査時の最新データ [注2]「M&Aほか」は、買収・出向・分社化の合計](/shared/images/hojin/column_article_1270310_12651_img_01.jpg)
神奈川県内についても、同様の傾向です。「神奈川県「後継者不在率」動向調査(2024年)」によると、2024年の親族内承継の割合は30.9%と、内部昇格に次いで2番目に高い値です。日本全国と同様に神奈川県でも3割以上の企業が親族内承継を選択していることがわかります。
![神奈川県 事業承継「就任経緯別」推移(2020年以降) 親族内承継[2020年]33.3%、[2021年]33.7%、[2022年]30.9%、[2023年(実績值)]29.5%、[2024年(速報値)]30.9% 内部昇格[2020年]31.9%、[2021年]33.4%、[2022年]35.6%、[2023年(実績值)]39.0%、[2024年(速報値)]38.4% M&Aほか[2020年]21.1%、[2021年]22.0%、[2022年]22.9%、[2023年(実績值)]19.2%、[2024年(速報値)]21.0% 外部招聘[2020年]7.9%、[2021年]7.2%、[2022年]6.1%、[2023年(実績值)]8.8%、[2024年(速報値)]5.8% 創業者[2020年]5.8%、[2021年]3.7%、[2022年]4.5%、[2023年(実績值)]3.5%、[2024年(速報値)]3.9% [注1]2022年までの数値は、過去調査時の最新データ [注2]「M&Aほか」は、買収・出向・分社化の合計](/shared/images/hojin/column_article_1270310_12651_img_02.jpg)
親族内承継の割合は相対的に見ると減少していますが、未だポピュラーな事業承継の選択肢のひとつです。
親族内承継の流れと成功のポイント
では、親族内承継はどのような流れで進めていけばいいのでしょうか。具体的なステップとスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。
1.後継者を選定する
まずは、なるべく早い段階で後継者を選定しましょう。
後継者候補がいたとしても、本人に事業を引き継ぐ意思がないことも珍しくありません。「おそらく継いでくれるだろう」と打診を先延ばしにしていると、断られた際に新たな後継者候補の選定が必要となり、想定以上に時間を要する場合があります。
まずは早めに本人へ承継の意思を確認しましょう。本人に継ぐ意志があったとしても、その家族が反対するケースもあるため、あわせて家族の理解を得られるように働きかけることをおすすめします。
また、後継者候補が複数いる場合は、「経営能力」「実績」「意欲」「第三者の評価」などの明確な基準を設け、選定しましょう。他の親族や社員が納得できる公正なプロセスが必要です。
2.株式や資産の承継準備をおこなう
事業承継時には、後継者の株式保有割合に注意が必要です。
後継者が議決権の過半数を確保できていない場合、株主総会での意思決定が単独ではおこなえず、経営権が不安定になる可能性があります。また、特別決議に必要な3分の2以上の議決権を持たない場合、定款変更や重要な経営判断を他の株主の意向に左右されるリスクも発生します。後継者が少なくとも議決権の50%超、可能であれば3分の2以上を確保できるよう、早めに株式の移転計画を立てることが重要です。
あわせて、事業用不動産など重要な資産を保有している場合は、その承継方法についても検討をおこないましょう。
3.遺言信託・生前贈与を活用する
株式や事業用不動産の円滑な引継ぎには、遺言信託や生前贈与の活用が効果的です。ただし法務や税務の観点で複雑なため、必要に応じて専門家へご相談ください。経営者の想いを汲み取った最適な提案を受けられます。
早めの計画と手続きでスムーズな事業承継を
親族内承継は、経営理念や価値観を引き継ぎやすい一方で、後継者の育成や資産承継などの課題に直面する場合があります。早めの計画と手続きでスムーズな事業承継を実現しましょう。横浜銀行でも、事業承継に関するご相談を承っております。金融機関や専門家の知見も活用し、次世代へのバトンタッチを成功させましょう。
関連記事
経営課題カテゴリ
経営課題テーマ
不明点を問い合わせる

