成功事例に学ぶ! 中小企業の新規開拓戦略
公開日:2025年7月25日
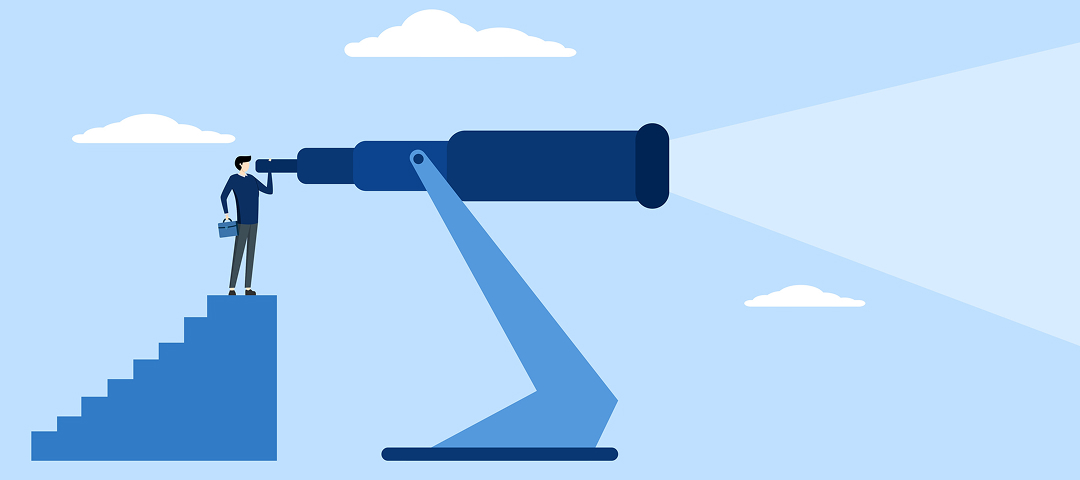
市場環境の変化が激しさを増す昨今、積極的な新規開拓の重要性が増しています。しかし、重要性を認識していても、実行に移せていない企業も多いのではないでしょうか。本記事では、中小企業における新規開拓の成功のヒントと事例をご紹介します。
中小企業に新規開拓が必要な理由
なぜ中小企業にとって新規開拓が重要なのか、おもな理由には次の2つが挙げられます。
企業の成長を実現する
1つ目は、持続的な企業成長の実現です。少子高齢化による人口動態の変化、感染症・天災などの予測困難な事態、AI等の新技術の発展により、消費者ニーズや市場環境の移り変わりが加速しています。既存の製品やサービスに対する需要も日々変化し、市場から淘汰されるものも少なくありません。
こうした状況下で中小企業が成長を続けるためには、既存の事業市場に固執せず、新しい市場への積極的な事業展開や新規開拓を常に検討していくことが必要です。
取引先の倒産のリスクを軽減する
2つ目の理由は、取引先の倒産や廃業のリスクの軽減です。帝国データバンク「神奈川県内企業「倒産リスク」分析調査(2024年)」によると、神奈川県内企業の倒産件数は542件で、前年比3.8%増となり、3年連続の増加を記録しました。
さらに、帝国データバンクの調査「全国「老舗企業」分析調査(2024年)」によると、老舗企業の倒産件数も高水準で推移しています。全国の老舗企業(業歴100年以上)の倒産件数は2024年9月時点で110件と、過去10年間で最も多かった2019年に並ぶ水準です。環境は厳しさを増し、業歴の長い企業であっても廃業や倒産のリスクが高まっていることから、先を見越した新規開拓によるリスクの軽減が重要です。
![[老舗企業倒産数の推移]2014年 81件、2015年 85件、2016年 100件、2017年 84件、2018年 86件、2019年 110件、2020年 98件、2021年 68件、2022年 65件、2023年 96件、2024年(1~9月) 110件(2024年9月時点) ※帝国データバンク 「全国「老舗企業」分析調査(2024年)」P6より引用および作図](/shared/images/hojin/column_article_1271051_12651_img_01.jpg)
中小企業の新規開拓の成功事例
では、中小企業はどのような戦略で新規開拓に取り組み、成果を出しているのでしょうか。中小企業庁が公開している成功事例の中から3つご紹介します。
(参考:ミラサポplus 中小企業向け 補助金・総合支援サイト「事例から学ぶ!「新事業展開」」)
水平型多角化:既存ノウハウを活かし類似市場に新製品を導入
まずは水平型多角化の事例です。水平型多角化とは、既存事業と類似した市場に、既存の経営資源やノウハウを活かして新製品や新サービスを投入する戦略を指します。家電メーカーがゲーム機を発売したり、オートバイメーカーが自動車の製造・販売を開始したりといった事例がこれにあてはまります。
ある印刷会社は携帯電話のカバーフィルムが主力製品でしたが、利益率の改善が課題でした。同商品で培った技術を活用して新たに開発したのが、女性向けのネイルシールやタトゥーシールです。これがヒット商品となり売上に貢献、さらに社内で一貫生産できる仕様により高い利益率を確保しました。
このように既存の設備やノウハウを活用し、比較的低いリスクで挑戦できる点が水平型多角化のメリットです。
垂直型多角化:バリューチェーンを川上から川下に拡大
次に、既存事業の川上もしくは川下の領域に進出し、成長拡大を狙う垂直型多角化です。繊維メーカーのアパレルブランドの立ち上げや、スーパーマーケットによるプライベートブランド商品の自社開発などの取り組みがその一例です。
ここでは、段ボールメーカーの事例を紹介します。もともと段ボール製造を事業としていた企業が、並行して部品の包装・梱包など庫内物流の請負事業を新たに展開しました。結果、既存顧客の発注する商品やサービスのすそ野が広がり、売上拡大を成し遂げました。
垂直型多角化は、既存の取引先や関係先がターゲットとなり、短期間での事業拡大が見込めます。一方、新たな設備投資やノウハウが必要なため、小規模からのスタートによりリスクを抑えることが重要です。
集中型多角化:既存資源を活かした新製品を新市場に投入
最後に集中型多角化です。自社が持っている経営資源やノウハウ、技術、設備を活かした新商品・新サービスを、新たな市場・顧客に投入する戦略を指します。
従来のビジネスモデルを転換した旅館では、広大な敷地という経営資源を活かし、サテライトオフィス事業を開始しました。安定した賃料と高い利益率により、現在では収益の新たな柱となっています。
このように集中型多角化は、既存の設備やノウハウを利用するため、事業化自体は比較的進めやすいとされています。一方、従来とは全く異なる市場・顧客へのアプローチ手法が課題となる場合が多いです。
中小企業の新規開拓で最初に実施すべきこと
先に紹介したように、新規開拓にはさまざまな戦略があります。
そのため、自社に適した戦略の立案が成功には欠かせません。
新規開拓は自社の強みの把握から
まずは、自社の強みを明確にしましょう。
自社の強みを知る1つの手法が、「SWOT(スウォット)分析」というフレームワークです。SWOTは下表のとおり、「S(強み)」「W(弱み)」「O(機会)」「T(脅威)」を指します。自社の事業状況を、内部環境のプラス要因「強み」とマイナス要因「弱み」、外部環境のプラス要因「機会」とマイナス要因「脅威」に分けて整理し、分析します。
ある小規模の印刷メーカーの場合は、下表のとおりです。
![[自社の内部環境]プラス要因(S)Strengths(強み) 短納期での印刷が可能、デジタル印刷により小ロットの注文にも対応 マイナス要因(W)Weaknesses(弱み) 一部の大口顧客への依存、一部の設備が古く、メンテナンスが必要 [自社の外部環境]プラス要因(O)Opportunities(機会) 個人向け印刷需要の増加、デジタル印刷需要の増加 マイナス要因(T)Threats(脅威) 印刷業界の競争激化、紙やインクなど原材料費の高騰](/shared/images/hojin/column_article_1271051_12651_img_02.jpg)
強みをもとにした戦略立案
SWOT分析で自社の現状を整理したら、内部と外部の要素を掛け合わせて「クロスSWOT分析」をおこないましょう。ここでは、先述の印刷メーカーについて考えてみます。
![[S(プラス要因)×O(プラスに働く外部環境)]強みを発揮し機会を活かす 小ロットに対応できる強みを活かし、個人顧客の印刷を積極的に受注する [W(マイナス要因)×O(プラスに働く外部環境)]弱みを克服し機会を獲得する 大口顧客への依存から脱却し、新規顧客層を開拓する [S(プラス要因)×T(マイナスに働く外部環境)]強みを発揮して脅威の影響を避ける 競争激化に備えて、短納期対応の強化により他社との差別化をはかる [W(マイナス要因)×T(マイナスに働く外部環境)]弱みを克服し、脅威の影響を最小限にとどめる 利益率の改善が見込めない場合は、事業を撤退し工場や設備を売却する](/shared/images/hojin/column_article_1271051_12651_img_03.jpg)
リソースの限られる中小企業が新規開拓する際は、特に「S(強み)×O(機会)」に注目した戦略の策定が効果的です。例えば、「小ロットに対応できる強みを活かし、個人顧客の印刷を積極的に受注する」にフォーカスすると、ECでオリジナルグッズの制作を受ける、個人クリエイターや小規模ブランドをターゲットにSNSでプロモーション活動をおこなうといった施策が考えられます。
外部の支援も活用し効率的な新規開拓を
環境が大きく変化する昨今、新規開拓の重要性は日々増しています。しかし、闇雲に行動するのではなく、自社の強みを分析し、ターゲットとする市場を明確にした戦略で、成功可能性を高めることが重要です。さらに精度を高めるためには、外部の専門家の支援の活用も効果的です。地域の事情に詳しい地元の金融機関も経営に関する相談を受けていますので、ぜひ活用をご検討ください。
関連記事
経営課題カテゴリ
経営課題テーマ
不明点を問い合わせる

