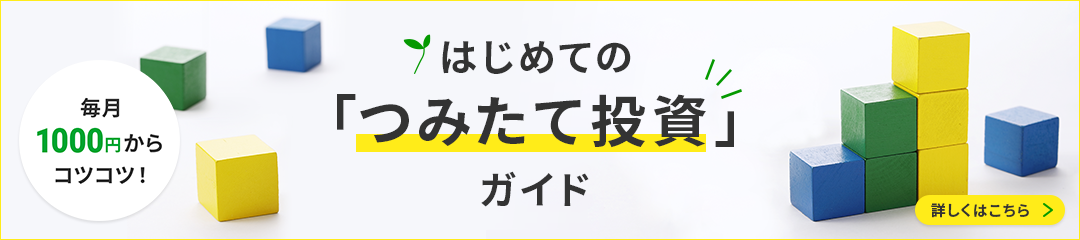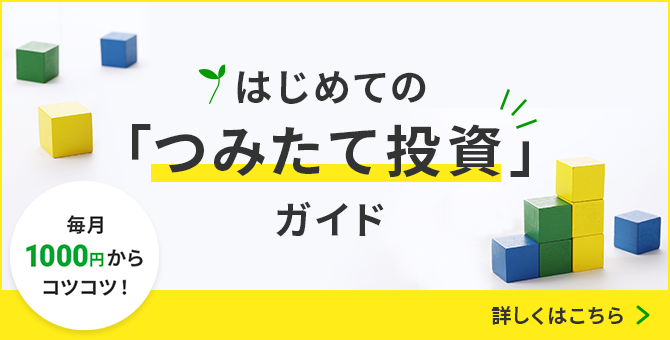2025.04.22
家計がピンチ?食品やガソリンの値段はなぜ上がるの?
- 提供
- 株式会社MILIZE
- 更新
- 2025年4月
食品や電気料金、ガソリンなどの値段が上がっているというニュースをよく耳にします。生活に必要なモノの値段が上がると家計への負担も大きくなるのではないでしょうか?
この記事では、継続的にモノの値段が上がる「インフレ」について、家計への影響と備え方をお伝えします。
食費や光熱費、ガソリン代はどのくらい上がっている?
はじめに、私たちの日常生活に必要なモノの値段がどのくらい上がっているかを確認しましょう。
①食品
2022年に入ってから、飲食店やスーパーなどが値上げをするニュースが相次いでいます。具体的な例を見ると、東京都では2020年と比べて2025年1月期に生鮮野菜が54.5%(※1)、生鮮魚介が34.0%(※2)値上がりしており、政府が決める小麦価格は2021年10月期から2024年10月期で7.7%上昇(※3)しています。
- ※1、2
東京の物価‐東京都区部消費者物価指数‐令和7年(2025年)1月分(中旬速報値)
- ※3
農林水産省「輸入小麦の政府売渡価格の改定について」(令和6年9月11日)
②ガソリン
全国平均のレギュラー価格は、2020年5月の底値124円が、2025年2月には184円を記録(※4)しており、1ℓ当たり60円も上昇しています。一般的な普通乗用車のガソリン容量を42ℓとすると、レギュラー満タンで給油した場合、2,520円値上がりしたことになります。
- ※4
経済産業省 資源エネルギー庁 給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)
このように、継続的にモノの値段が上がることを、インフレといいます。インフレ下では、これまでと同じ水準の生活をしていても生活費は上がってしまうため、家計にとってはマイナスです。
なぜ、モノが値上がりしているの?
では、なぜ今インフレが起こっているのでしょうか?その要因を2つ解説します。
①円安ドル高
1つ目の要因は、円安ドル高です。
直近の円安の背景には日米の中央銀行の金融政策の方向性の違いがあります。
近年日本や米国は、金利を低く抑えることで経済活動の活発化を狙ってきましたが、2022年3月以降、米国では新型コロナウィルスの影響による需供のバランス悪化やウクライナ情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の上昇を背景としたインフレを抑制するために、2023年7月までの間に政策金利の引き上げを11回実施しており、政策金利は0.25%から5.50%まで上昇しています。
一方、日本の中央銀行である日銀は、2024年3月の金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除を決め、利上げをおこないましたが、依然として低金利の環境が続いていることには変わりありません。
このような背景もあり、市場では金利による収入が低い円を手放し、金利による収入が高いドルを求める動きが起こります。為替が円安に動くと、企業が外国から商品を輸入する際の価格が上がるため、私たち消費者が国内で商品を購入する際の価格も上昇につながります。
②エネルギー高
2つ目の要因は、エネルギー価格の上昇です。
ガソリンや電気・ガスなどのエネルギー価格の上昇も、私たちの生活に大きな影響を与えています。例えば、ガソリンは石油を採取・精製することで作られますが、新型コロナウィルスの感染拡大からの回復局面における需要増や石油生産国の生産抑制、ウクライナ侵攻に伴うロシアへの経済制裁による流通の停滞などが理由で価格が上昇しています。加えて石油のほとんどを輸入に頼っている日本では、円安もガソリン代の高騰に大きく影響しています。
物価上昇に有効な対策は?
では、私たちはこの物価上昇に対してどのような対策をすればよいのでしょうか。
その方法の1つとして、「資産運用」があげられます。
例えば、1年で物価が10%上昇する場合、現在100万円で買えるモノの値段は1年後には110万円になります。対して現在の日本では低金利が続いているため、今手元にある100万円を1年間円預金に預けても、100万円は100万円(※1)のままです。
お金自体の「額」は100万円で変わらなくても、お金の実質的な「価値」は10%目減りすることになります。
この期間、手元の100万円を半分に分けて、一方は円預金、もう一方は資産運用に回したとします。資産運用は元本割れリスクを伴うため、実際に検討する際は商品内容やリスクなどを理解する必要がありますが、仮に年6%の利回りで運用できた場合は50万円が1年後に53万円(※2)になります。もともと100万円だったお金は、円預金50万円(※3)+資産運用に回した分の53万円=103万円で、モノの値上がり10万円に対して3万円分は物価上昇に対応できることがわかります。
- ※1、2、3
金利、税金、資産運用にかかる各種手数料等は考慮していません
「資産運用」と一言でいってもその方法は様々ですし、商品ごとにリスクの程度も異なります。何年後にいくらくらいに増やしたいか、どの程度のリスクなら許容できるか、運用の目的やご自身のお考えに合わせた適切な方法を選ぶことがおすすめです。
2025年3月時点の法令に基づき更新
まとめ
現在のような物価上昇は、過去に何度も起こっています。
今回はその対策として「資産運用」をご紹介しました。とはいえ初心者の方は、資産運用なんて怖い、簡単なことではないと感じるかもしれません。
ですが、少額からはじめられる投資信託などを通して資産運用をおこなうことも可能です。
いつかは始めなきゃ…と考えてはいてもなかなか一歩踏み出せないのが資産運用の世界。
横浜銀行では「初めてのことで何から考えれば良いかわからない」「メリットとデメリットを1から知りたい!」という方にもわかりやすくご説明しています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

ご留意事項
- この情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。なお、掲載されている見解および図表等は当資料作成時点のものであり、その正確性、安全性、将来の市場環境の変動等について保証するものではありません。
- これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者、執筆者および当行は一切の責任を負いません。
投資信託についてのご注意
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。
- 投資信託は、次の要因により、お受け取り金額が投資元本を下回ることがあります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の値動き(価格変動リスク)があります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の発行者の信用状態の悪化によるリスク(信用リスク)、国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク(カントリーリスク)があります。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク(為替変動リスク)があります。
詳しくは、各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込み)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.2%(税込み)の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。これらの手数料等は、各ファンドにより異なるため、具体的な金額、計算方法をあらかじめ表示することができません。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。(2024年12月9日現在)
- ※
一部ファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
- ※
- 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 〈はまぎん〉マイダイレクト投資信託サービス(インターネットバンキング)では、一部申込手数料のキャッシュバックがあります。
- 一部のファンドには、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 横浜銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は設定・運用を投資会社がおこなう商品です。
- お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書および目論見書補完書面は横浜銀行の本支店等に用意しています。
記事をシェアする