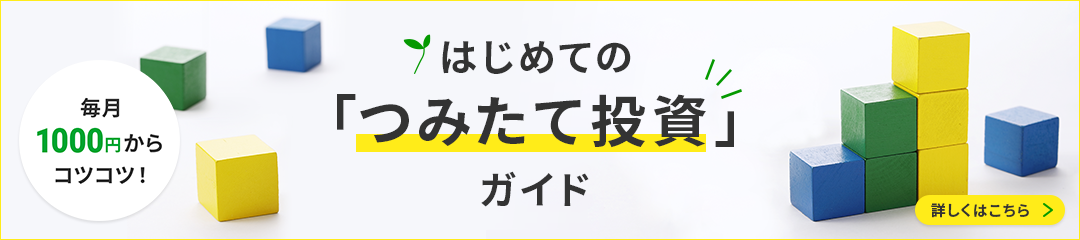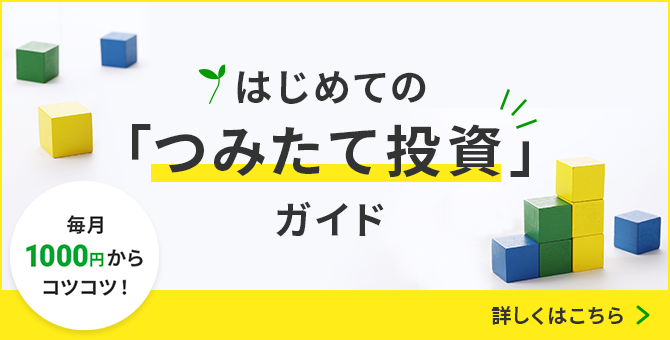2024.08.29
資産形成って必要なの?
- 監修
- 株式会社MILIZE
- 作成
- 2024年8月
私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。預金金利は上昇傾向にあるものの、利息だけでお金を増やすことは依然として難しい状況です。
私たちを取り巻く環境
私たちの生活はさまざまな要因により大きく影響を受けます。

将来必要な生活費は増加傾向にあり、預金などの安全資産だけでは将来にそなえた資産づくりは難しいかもしれません。
お金を準備するには?
まずは、ライフイベントにかかるお金が「いつ」「どれくらい」必要になるか整理し、お金の計画「マネープラン」を立ててみましょう。「マネープラン」をあらかじめ立てておけば、実現にむけて準備する手段や方法を、長期的な視点でイメージしやすくなります。
ライフイベントごとに、どれくらい費用がかかるのでしょうか。









「人生の三大資金」といわれるのが、住宅資金・教育資金・老後資金です。
住宅資金は、土地付き注文住宅の場合、約4,694万円、教育資金は幼稚園から大学卒業まですべて私立の場合、約2,660万円かかるといわれています。
ゆとりある老後を過ごすために必要なお金は、約38万円(月)です。
夫婦2人で老後生活を送る場合、セカンドライフが25年と仮定すると、38万円×12か月×25年=11,400万円を用意する必要があります。(※)
- ※
年金受給は含んでいません。

- ※
利息・税金などは考慮しておりません。
「マネープラン」が立てられたら、どのくらいの期間・利率で運用すればゴールに近づくことができるか、具体的な戦略を立てることができます。
仮に目標額を1,000万円とし、60歳までに貯蓄したい場合、積立をはじめる年齢が早ければ早いほど月々の積立額は少なくてすみます。
![[100万円を10年間確定利回りで運用した場合(複利)の受取額のイメージ]年1%で運用した場合:約110万円 年3%で運用した場合:約134万円 年5%で運用した場合:約163万円 年10%で運用した場合:約259万円 年10%で運用した場合は年1%で運用した場合の約2.35倍](/column/shared/images/column/topics/topics_1260124_img_012.png)
- ※
算出に当たって利息は毎月の複利計算で算出していますが、税金・手数料等を考慮していない為実際の運用とは異なります。また、将来の運用成果を約束するものではありません。
100万円を10年間確定利回りで運用した場合(複利)、年1%で運用した時の受取額は約110万円です。対して、年5%で運用した時の受取額は約163万円、年10%だと約269万円と年1%で運用した場合よりも、最大で約160万円の差となります。
少しでも高い利回りで運用することで、運用した時の受取額の差は大きくなります。
まとめ
一人ひとりの理想的なライフプランは異なります。それぞれの目標や理想の暮らしを叶えるために、いまから資産形成が必要です。
資産形成のために、貯蓄や運用などいろいろな方法を検討してみましょう。

ご留意事項
- この情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。なお、掲載されている見解および図表等は当資料作成時点のものであり、その正確性、安全性、将来の市場環境の変動等について保証するものではありません。
- これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者、執筆者および当行は一切の責任を負いません。
記事をシェアする