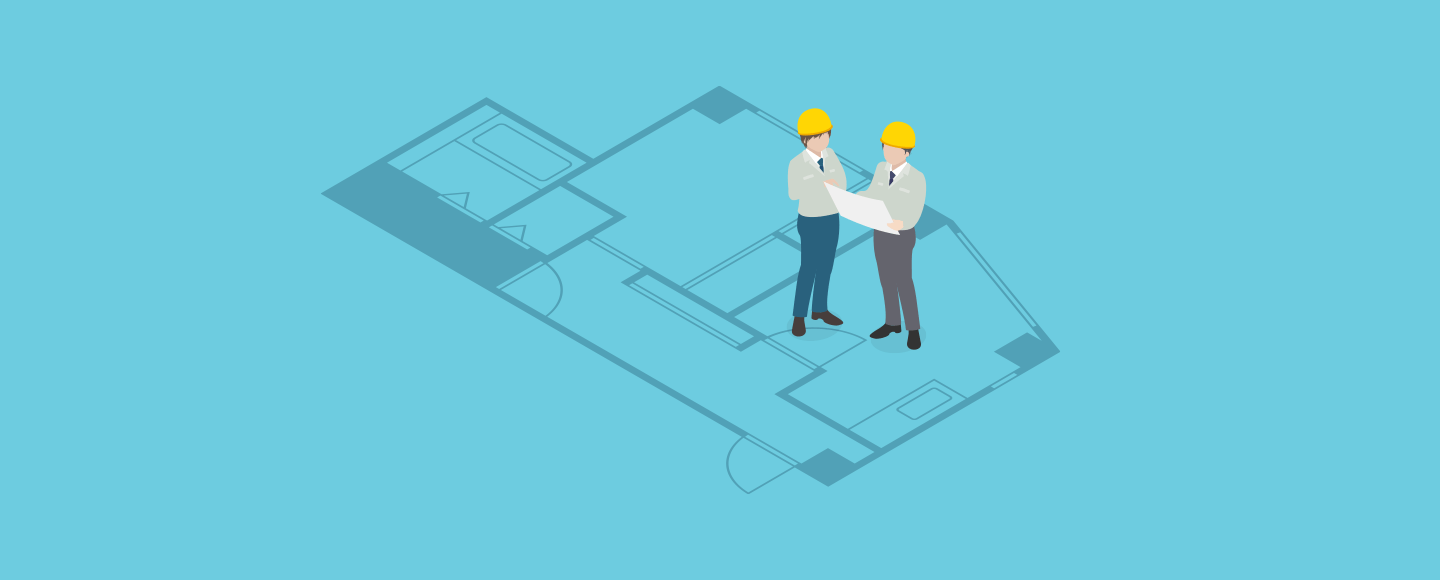
2023.12.18
地震対策のリフォーム、何をすればいいの?
- 監修
- 株式会社MILIZE
- 更新
- 2023年12月
日本で“災害”と言えば、真っ先に思い浮かぶのは地震ではないでしょうか。東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)は、今なお私たちの記憶に新しいところです。
今後、30年の間に約70%の確率で発生すると予測されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震は大いに気になるところです。
首都直下地震では約61万棟の住宅が全壊すると言われています。これは、東日本大震災で全壊した住宅の約5倍に相当します。
南海トラフ巨大地震では、東日本大震災で全壊した住宅の約20倍にあたる約238.6万棟の住宅が全壊すると想定されています。
地震は避けられません。しかし、その地震からの被害を最小限に食い止め、住宅を残すことができたとするならば、おそらく、その被害からの立ち直りも早いはずです。
そのためにどんなことができるのか、いくつかの地震対策をご紹介します。
建築基準法で定められる耐震基準は、大規模地震を経験する都度、改正が繰り返されています。
1981年6月に改正された新耐震基準ですが、基準を満たしている木造住宅でも震度6強で倒壊する可能性が高い住宅が相当数あることが判明し、2000年6月に大幅に耐震基準が見直されています。
この時指摘されたのが「基礎」「筋交いなどの接合部」「耐力壁」についてです。
つまり、2000年5月までに建築された住宅は、これらの箇所を補強する必要があるかもしれない、ということです。
基礎の補強
住宅の基礎は一般的にコンクリートと鉄筋でできています。築年数のたった住宅では玉石基礎の住宅も見受けられますが、そのような場合は、鉄筋コンクリート造の布基礎に替える必要があります。また、コンクリートは劣化が進むとひび割れが生じます。そのひび割れから雨水が侵入すると、中の鉄筋を錆びさせ、著しくその強度を低下させます。このひび割れの対策としては、基礎の側面に炭素繊維シートを貼り付ける工法などがあります。
壁の補強
木造住宅では、柱や梁、筋交いなどの接合部を補強するために金物が使われています。その金物を強度の高いものに交換したり、金物そのものを増設したりすることによって壁を補強し、住宅の骨格を強固なものにする方法です。
壁の配置
一般的な木造住宅では柱と柱を筋交いと呼ぶ木材で斜めに支え、強度を持たせています。この筋交いを補強するために耐力のあるボードで壁を作り、柱と柱を面で支えることで住宅の耐震性は大幅に向上します。この耐力壁を建物の角や間口の広い面にバランスよく配置することにより、建物全体の強度をあげることができます。
上記の例は、木造住宅の耐震性能を上げる方法です。建物の築年数や規模、構造によりかかる費用はまちまちですが、一般的な2階建て木造住宅の耐震工事の工事費用は全体の半数以上が190万円以下で、100~150万円程度が最も多くなっています。
建物の補強(リフォーム)の他に、地震対策として電力の確保を検討しておきましょう。
大規模地震の場合、電気の復旧までに1週間、地域によっては1か月以上かかると言われています。この長期停電に備えるためには、太陽光発電と家庭用蓄電池を組み合わせたシステムの導入などが効果的です。
家庭用蓄電池の導入にあたっては、補助金の制度がある自治体もありますので、検討してみましょう。
最近は、ハイブリッドカーや電気自動車から家庭に非常用電源を供給するシステムも開発されています。給電機能を備えた車両とは別にV2Hという機器が必要となりますが、自治体によっては補助金が交付される場合もあります。
いくつか地震を中心に災害対策のリフォーム事例を見てきました。ご自宅の状況に合わせて何が必要か、ご検討ください。
いずれにしても、災害対策にはまとまった資金が必要です。家計と相談しながらになると思いますが、リフォームローンの利用を検討してはいかがでしょうか。資金が貯まるまでリフォームを先延ばしにしている間に災害にあってしまっては、もとも子もありません。資金計画を考えながら安心な住環境を手に入れましょう。
横浜銀行ではリフォームローンも扱っています。具体的なリフォームの内容や金額が決まっていなくても仮審査を受けられますので、あらかじめ仮審査を受けて借りられる金額を把握しておくのも良いかもしれません。
記事をシェアする